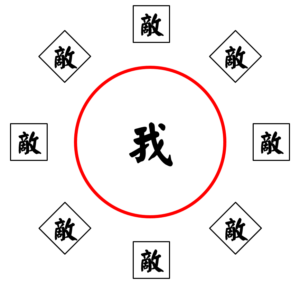立身流第22代宗家 加藤 紘
令和4年(2022年)6月6日 掲載/7月4日 改訂(禁転載)
1、福澤先生が立身新流を晩年まで嗜(たしな)んでいたことは、拙稿「福澤先生と立身新流居合」(拙著「立身流之形 第二巻」144頁以下、平成30年1月31日発行・以下、形二という)に記しました。
先生は明治23年7月8日付(先生満56歳)の書簡で「…又少年の時中村庄兵衛先生に學び得たる居合を以て運動致し、近来は少々上達の様に覺え候得共、何分にも立身新流の先生無之して惡しき處を直して貰う方便を得ず残念に存候。是れは運動の事なれども…」(福澤諭吉全集第18巻401頁 昭和37年5月10日発行 著作権者慶應義塾)と述懐されています。
中津藩内で立身新流は普通に「新流」と呼称されていました。
2、私の手元に以前、市川生央氏から頂いた明治40年6月の「武徳誌 第2巻6号」(写し)があります。
(1)その78頁に、(大日本武徳会)「…大分支部總會…は五月十八 十九の兩日…擧行せり…」、その79頁に「…演武…は第二日劍術…」とあり、そこには
立身新流居合 _/¯ 佐野恕平
立身當流居合 ¯\_ 恩田友十郎
との記載および
東軍一刀流
長刀入身 佐野恕平
との記載があります。
この記載から、立身新流の佐野恕平と立身當流の恩田友十郎が一緒に居合を演武し、佐野恕平は東軍一刀流の演武も行ったことがわかります。
(2)「恩田友十郎」の名は「物語 中津藩の歴史 下巻」(原田種純著 昭和54年12月5日発行)の「幕末中津藩士人名録」中285頁に「高百六十石」として記されています。
恩田姓は中津藩内に数家あり、その一は立身當流の家で(拙著「立身流之形第一巻改定版」12頁「立身流伝系図Ⅱ」参照 令和4年(2022年)1月31日発行・以下、形一という)、「中津藩史」(著者兼発行者 黒屋直房 昭和15年11月11日発行)569頁には「立身流抜合師範ノ系」とされています(「當流ト改ム」の系列として。他に「新流ト改ム」の系列がある)。
「恩田友十郎」はその係累の人でしょう。
「佐野恕平」は、同書568頁の「東軍流長刀師範ノ系」の最後尾に「佐野恕平種則」と記載されている人物でしょう。
(3)この武徳誌の記載から次の事柄がわかります。
①立身新流居合と立身当流居合には、共同して演武できるほどの同質性と交流があった。
②この二流は福澤先生没(明治34年)後も大日本武徳会で演武されていて、演武者は旧藩時代の師範家の武術家本人とも思われる専門家である。
3、拙稿「立身流門を主とした佐倉藩士と警視庁」(形二・132頁)で、明治期の警視庁で活躍した立身流門の人々について記しました。
福澤先生の居住された東京に立身流の、そして故郷の大分には立身新流、立身当流の先生方がおられたわけです。
福澤先生にそれを知るきっかけがあったならば、と残念でなりません。
4、「惡しき處を直して貰う」とすればどのような「處を直して貰」いたいのか、先生の期待はどの辺にあったのかを検討してみます。
(1)まず、先生の居合をうかがい知るよすがとなる記述をみてみます。
①「かねて少し居合の心得もあるから、どうしてくれようか、これはひとつ下からはねてやりましょうという考えで、…此方(こっち)も抜いて先を取らねばならん、…」」(「福翁自伝」226頁 2009年4月1日発行 著者福沢諭吉 校注解説富田正文 発行者慶應義塾 以下自伝という)。
②「…四尺ばかりもある重い刀を取て庭に下りて、兼て少し覚え居る居合の術で二三本抜て見せて…」(自伝229頁)
③「次の運動は即ち居合である。これは先生がまだ中津にいた少年のとき、士族として何か武藝を學ばねばひとでないやうで風が惡いといふので、中村庄兵衛といふ居合の師匠に就て稽古されたものである。」(石河幹明「福澤諭吉傳」第四巻252頁 岩波書店1932年7月15日第1刷発行 2001年1月15日第7刷発行・以下、傳という)
④「…居合と米搗(こめつき)と雙方の兼行は過激…」「「無論力を要する米搗の方である」といひたるに、…居合の方が米搗よりは餘程骨が折れるものだ。…」(傳257頁)
⑤「先生の居合は少年のとき師匠に就て稽古せられたのみで、その後はたゞ運動のために獨りで試みられたのみ…」「先生は食後には必ず居合抜をなさるので、…長い刀の柄に箸をお立てになって、其箸の下に落ちない中に、その長い刀の鞘を拂ってこれを二つにお斬りになったり、又は其刀を抜く餘地のない窮屈な處でお抜きになったり…」「父菊五郎も…先生に居合の呼吸を伺った…」、(米搗)「これも呼吸があるもので、お前たちのはたゞ力でやらうと思ふからいけないのだ。」(傳257, 258頁)
⑥「…運動に居合を好み時々米搗きまでせらるゝので筋骨逞しく…」(傳540頁)
⑦「居合には六つの型があるそうで、先生は一と通り此六法を繰返してから休まれることにしてゐましたが、見てゐると、寒中單衣一枚にも拘らず、五六十本切付ける中に額から汗が流れて来るほどでした。先生の話に「…私の居合も稍や極度に近いものと見える…」といはれました(伊東茂右衛門談)」(傳811頁)
⑧「少し前屈みながら、肩幅の広い福澤が、…跣足(はだし)で(草履ばきであったか?)立ち、かけ声とともに刀を抜き、踏み込み踏み込み、刀を振り回し、また鞘におさめる。同じことを幾たびもくり返す。…福澤は千本抜き、千二百本抜きの記録を手記している。…千二百本抜きの時間は…。また、居合の間に当然一定の場所を往き来する。「足をはこばすことも五千二百間、凡二里半ばかりなり」と福澤は或る手紙の中に書いている。それが明治二十七年、福澤の数え年六十一のときのことである。」(山﨑元「慶應義塾のスポーツ医学――社会を先導する役割――」中に引用の小泉信三の文・「三田評論」第1150号63頁乃至64頁 平成23年11月1日慶應義塾発行11月号・以下、評論という)
(2)これらの記述をみると、先生は、少年の頃、立身新流居合を少し師につき稽古したものですが、ずいぶん好きで運動として日常居合を一人続けました(前掲拙稿・形二・144頁以下参照)。数抜を続け、時には曲芸のようなことをして人を喜ばせました。居合は力を要して骨がおれるもので、米搗と同じく力だけでなく呼吸が必要との御認識のようです。先生は実戦にもある程度の自信があり、自分でも極度に近いと感ずる程の域に達していました。満60歳になっても数抜千本を通し続けました。
(3)先生の記述から、先生の居合がどのようなものであったのかを探るヒントとなる諸点をあげてみます。
1)先生の数抜や居合の居組、居合刀などについては拙稿「福澤先生と立身新流居合」(形二・144頁以下)で触れました。
また、そこに書いた通りとすると、先生は居組も抜かれ、その居組は序であって初心者向けの居合の形だった可能性が強いと思われます。
2)四尺ばかりもある重い刀(前記②)、運動(前記③⑤)
現存する先生愛用の居合刀の長さ重さ(形二・145頁)は、先生の体格からすれば立身流としては普通ですが、一般に使用されるものと比べれば長く重いものです。
ちなみに、現在私と息子の次期宗家・敦がそれぞれ使用する居合刀二振(銘・伯耆国住義輝、國澤兼俊)の長さ重さは、拙稿「立身流に於る「…圓抜者則自之手之本柔二他之打處強之理…」(立身流變働之巻) 形二・94頁に記したとおりです。しかし、2人とも十代の頃の居合刀(銘・濃州住藤井兼音)は、刃渡り2尺3寸7分(約72.1センチ)、鞘を払っての重さ1,057グラムです。先生の愛刀より2.2センチ短く、約105グラム軽いことになります。
本来、技が身につくまでの間、初心者が重く長い刀を使用することは避けねばなりません(形二・94頁)
重い刀をその域に達してない人が振り回し続けるのは、単なる運動としてならば話は別ですが、武道武術の技の体得の面では不器用さが増すばかりです。
数抜に関しては後にふれます。
頭書の文でも「居合を以て運動」とあり、先生の居合は、武術武道の稽古修行というよりも運動目的でした。
3)其箸の下に落ちない中に、その長い刀の鞘を拂ってこれを二つにお斬りになったり、(前記⑤)
この話は、形一・6頁の「余興を求められ、腕組した両手を堅く縛らせて抜刀し、これは居合ではなく曲芸ですと恥じた」加藤久の逸話と相通じます。
このようないわゆる余興や物を対象とする技術は、対人関係である武道としての居合とは直接の関係はありません。そのことのみの練習でも、手慣れれば武道家でなくともできるようになるでしょう。
船越義珍先生の「空手道一路」(昭和31年10月1日発行)から引用します。
「なる程、空手をやる人が、普通の人には簡単に割れないような厚い板を、十何枚も割ったり、瓦を何枚も重ねて割ったりする。が、この程度のことなら練習次第で誰にもできるのである。」(21頁)
「空手は立派な武道なのだから、板を割ったり、瓦を砕いたり、肉を千切ったり、肋骨を砕いたり、そんな枝葉末節のことを自慢する人があったら、それは本当の空手を知らない人だと思って間違いない。」(22頁)
上記文章は「「板割り」「瓦割り」というようなことはあくまでも「試し」であって空手の本領ではないし、ましてや秘術などでもない。むしろ空手としては埒外のものである。」の文章との関係で記されていますから、居合の面でいえば試斬に対応する文ですが、いずれにしても埒外であることは同じです。
4)力を要する(前記④) 力でやらうと思ふからいけない・呼吸(前記⑤)
武道動作は呼吸との一致から始まります(拙稿「立身流に学ぶ~礼法から術技へ~」形二・89頁)。そして武道の奥義は「呼吸ヲ以テ打ツ」ことです。「呼吸ヲ以テ打ツ」ことができるようになる前段階は「躰ヲ以テ打ツ」であり、更にその前は「手ヲ以テ打ツ」で、しかも「力強クシテ手足堅ク」するのは厳禁です(形二・96頁・立身流秘伝之書)。
⑤での「呼吸」の意味は、あるいは師の中村庄兵衛から授かった上記「呼吸ヲ以テ打ツ」の意味なのかもしれません。しかし、「力を要する」との記述や次の5)の記述からすると、ここでは武術としての呼吸ではなく、上記3)に示されるような単に手慣れていることを意味していると思われます。師匠がおらず一人で数抜を重ねたことなども併せみると、単に数をかけて手慣れることから取得するコツ(形二・94頁参照)にすぎないものではなかったでしょうか。
5)筋骨逞しく(前記⑥)
生涯「先生は今で言えば身長173センチ、体重68キロ」(評論62頁、自伝315頁)だったとのことで、いまの私と比べると身長は同じで体重が1キロ多いだけです。
ところで、居合を好むことが必然的に「筋骨逞しく」の結果を生ずるわけではありません(形二・94頁参照)。「運動」と武道武術との相違ともいえます。
ここの書かれ方は、武道居合に詳しくない人による印象表現だったのではないでしょうか。
本当に居合のおかげで「筋骨逞しく」なったのだとすると、「ただ力でやらうと思ふからいけない」と頭ではお分かりになっていながら、先生ご自身、技でなく力でやっておられたのでないかと推察されます。仮に言葉であるいは目で見てある程度わかり得たとしても、自分の身体ではできないのが、技・業・芸です。頭で理解できたことをどうすれば自分が実現しうるか、ここでも師が必要となります。
6)少し前屈み(前記⑧)
「少し前屈みながら、肩幅の広い福澤が」、と続きますから、意図的に前屈みにしているのではなく、体格として「少し前屈み」だったのでしょう。
もし体格姿勢でなく、技としての姿勢だったとすると問題です。「竪1横一」(形二・89頁)に反するからです。
業としての姿勢は、歩くときは勿論、走るときも腰を曲げず、屈(かが)みません。
7)数抜(前記⑧、形二・144頁)
形二・94頁に「…数抜…の数の多いものは、原則、相当に身のこなれた者がすべきです。…個癖を身につけてしまうことにもなりかねません。特に見てくれる人のいない一人抜は要注意です。」と記したとおりです。
未熟な者に数抜をさせると、疲れてきて力が抜けるのはよいのですが、樂をしようとしてごまかし必ず技が崩れます。そのごまかしの技や、未熟な技がそのまま矯正不可能な個癖として固まってしまう恐れがあります。
数抜の最中に、形・技が乱れた場合は直ちに矯正するか、止めさせます。勿論、「形がくずれた場合は本数には入れ」ません(加藤髙「古武道に学ぶ心身の自由(三)」形一・174頁)。
何千本抜いても、何万本抜いても、それだけで、その人が「名人」だというわけではありません。むしろ、やればやるほど、名人に至る道からはずれていく場合が多いのです。そうなると、美しい技を求めても、その実現は不可能です。
数抜はあくまでも稽古の、先生の場合は運動の、一方法にすぎません。先生はそれらをよく理解した上で、工夫を重ねつつ、数抜を続けていたのでしょう。
関連立身流歌を形二・94頁に二首あげました。
又、前出義珍先生の言葉を参照して下さい。
(4)要は、先生自らの御認識では「近来は少々上達」(本稿冒頭文)していたり、「極度に近い」(前記⑦)と思えていたのですが、「惡しき處」がないはずないからそれを「直して貰う」先生の意図です。
その「惡しき處」とは、教えを受けずにただ手慣れていっても、そして、いかに自分で工夫を加えても自己流になるだけで、個癖に陥らざるを得ない、その自分だけではどうしようもない個癖の矯正を願ったのでしょう。
立身流序之巻から引用します。
「…然亦取之有習若其不習而取之其剣縀雖為莫邪亦何益兮」
(しかれども また これをとるに ならいあり。もし それ ならわずして これをとらば そのけん よし ばくやたりといえども また なんぞ えきせん。…)
これと同一の文章が立身新流序之軸にも記されています。
5、先生の立身新流についての記載から他の興味深い点を挙げてみます。
(1)下からはねて…抜いて先をとらねばならん(前記①)
立身流居合で、これに該当するのは向の陰です。
立身新流の居合には、陰の動きも伝わっていて先生も学んだことがわかります。
(2)刀を抜く餘地のない窮屈な處でお抜きになったり(前記⑤)
立身流で言えば「外」(拙稿「立身流に於る形・向・圓・傳技・一心圓光剣・目録「外」(いわゆる「とのもの」の意味)」形二・112頁以下参照)にあたるもので、特殊状況下での心得からの一つでしょう。
立身流の立合目録や居合目録から窮屈な所で抜く方法を羅列してみると、落差抜様之事・同鞘共気不付様抜出様之事・壁添抜様之事・人込抜様之事・細道抜様之事などがありますが、先生のなさったものがそのどれであるかは不明です。
「外」は本質を求めるための形ではなく、単なる心得にすぎません。見せるためだけにこれらを行うということは、前記した曲芸に通ずることにもなります。
(3)居合には六つの型があるそうで(前記⑦)
立身流居合は、立合でも居組でも、表之形の序・破・急でも陰之形の初傳・本傳・別傳でも、八本で一組です(形二・145頁参照)。言い換えれば「八つの型」です。内容は、向・圓・後向・後圓・前後・左・右・四方です。
「六つの型があるそうで」というのが誤りで「八つ」だったとすれば、立身新流居合の形の構成は立身流と全く同じです。
立身新流の居合が六本だったのだとすると、多分、左と右の欠落した六本だったのでしょう。また、前後は、走らずに、歩みの動きだったのでしょう。
(4)かけ声と共に刀を抜き(前記⑧)
立身流居合は無声ですが、数抜では「ヤー・エーイ」と発声し続けます。前へ進みながら、「ヤー」で抜刀し「エーイ」で斬撃します。形は向・圓の立合の破です。元の位置に後進しながら納刀します。納刀が終り左手が下がると、直ちに左手が上がり、前進が始まります。
かけ声があるのは立身流の数抜そのものです。
(5)踏み込み踏み込み、刀を振り回し(前記⑧)
少々違和感のある表現ではありますが、ここでも立身流の立合の特徴が示されています。
立身流居合の立合は歩み(あるいは走り)の上に乗っています。それを示しているのでしょう。
このことが必然的に、次の(6)に連なっていきます。
(6)…千二百本抜きの時間は…。また、居合の間に当然一定の場所を往き来する。「足をはこばすことも五千二百間、凡二里半ばかりなり」(前記⑧)
歩みの上に業が乗っている立身流の立合だからこそ、又、数抜だからこそ「当然」なのでして、他流ではこのように言うことはできないと思われます。
明治27年先生61才の時の数抜記録は1,200本でした。
5,200間は9,362m、二里半は1万mですから、1,200本で1万メートルとすると1本8m30、数抜は前進後退を繰り返しますから、1本で約4メートルを行き、又、戻っています。
数抜は一旦始まると、食事(塩がゆ)の為の休止等の区切りまで、前進後退の歩きづめで足が止まることはありません。
正に立身流数抜です。
(7)数抜は立合です。そして、前述のとおり、先生は居組の序をおりふしドタバタやっていました(自伝313頁)。
つまり、立身流居合と同じく立身新流居合にも立合と居組があったことがわかります。先生はその双方を続けられたわけです。
6、総括
以上、先生の「惡しき處を直して貰う」気持ちが垣間見えるようです。
自分なりに努力し工夫し、それなりに上達はしたのですが、自己流のため、それ以上を望むことが不可能であることを自覚し、あらためて基本からの真の技を希求したのでしょう。
先生が「稽古」の語を使われるのは自伝313頁の「中村庄兵衛という居合の先生について少しけいこしたから、…」と記される箇所だけです。その後の居合は全て「運動」と記されていて、先生にとっては稽古と言えるものではなかったのです。
先生は、自分で自分を導けるまでの域に達していなかったことが「残念」だったのではないでしょうか。
先生のすばらしさは、自分の至らなさを理解なさっていたことにあります。
以上
(本稿の資料蒐集には、前記市川氏、日向一泰氏、小暮達夫氏および立身流奥傳八角敏正氏のご協力を得ました)